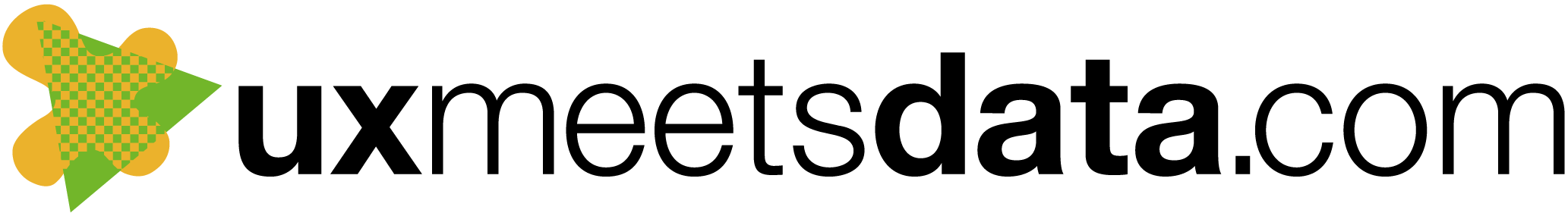UIのデジタル化。
ユニバーサルデザインという言葉が日本で流行したのは、1997年のグッドデザイン賞においてユニバーサルデザイン賞が設置されたことがきっかけと言われています。それから20年余りが経過し、この言葉を耳にすることは少くなりました。ブームというのは元来そういうものですが、一般的な考え方として定着したとも言えます。
一方、この20年余りでデザインをとりまく環境は大きく変化しました。あらゆる情報はウェブサイトやモバイルアプリで取得することができ、多くの券売機やATMの操作パネルはタッチパネル化されています。つまり、ユーザーインターフェース(User Interface:UI)のデジタル化が進んでいるわけです。なお、UIがPCやスマートフォンの画面を意味するという誤解がありますが、ユーザーとモノのインターフェース(境界線)のことなので、黒電話のダイヤルもAIスピーカーの音声認識も、広い意味ではすべてUIです。
そしてUIのデジタル化はパーソナライゼーション(Personalization)1)再考するパーソナライゼーションを可能にしました。それは一人ひとりのユーザーに最適化することであり、ユニバーサルデザインの対義語ともいえます。
このようなデジタル時代において、ユニバーサルデザインのもつ意義とはいったいどこにあるのでしょうか。ここで再考してみたいと思います。
能力差を問わず利用できるデザイン。
ユニバーサルデザイン(Universal Design)とは、文化・言語・国籍や年齢・性別などの違い、障害の有無や能力差などを問わずに利用できることを目指した建築・製品・情報などのデザインのことで、ノースカロライナ州立大学のロナルド・メイスによって1985年に提唱されたものです。
ノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンターによるユニバーサルデザインの7原則は以下となっています。
- どんな人でも公平に使えること。
- 使う上での柔軟性があること。
- 使い方が簡単で自明であること。
- 必要な情報がすぐに分かること。
- うっかりミスを許容できること。
- 身体への過度な負担を必要としないこと。
- アクセスや利用のための十分な大きさと空間が確保されていること。
ユニバーサルデザインの代表例は、シャンプーの容器のギザギザの印でしょう。これは頭を洗っていて目が見えないときでもリンスと区別できるようにつけられたものです。つまり、目が見えない状態は障害の有無にかかわらず起こり得るので、それを考慮したデザインということです。自動車のアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故があとを絶ちませんが、目の届かない場所での操作という意味では同様でしょう。

一方で、誰もが使いやすいデザインというのは理想主義で、あるわけがなく、逆に多様性を許容せずに規格にしばりつけるものである、という批判もあります。パーソナライゼーションは、多様性に対して個別に最適化する考え方であり、ユニバーサルデザインの対義語でもあり、補完するものでもあります。
デジタル時代における展開と意義。
とはいえ、ほとんどのUIはデジタル化されていませんし、すべてのモノをパーソナライズすることは不可能です。たとえ技術的に可能であっても、コスト的に見合わないことがほとんどでしょう。ユーザーの身長によって高さを自動調整する男性用小便器がたとえ開発されたとしても、普及することはおそらくありません。
パーソナライゼーションに対する過度な期待は、ユーザーの普遍的な課題や行動特性を理解することの重要性から目をそむけさせる危険性があります。実際、マーケティング領域ではパーソナライズ指向が強く、個々の行動特性の理解には熱心ですが、普遍的な行動特性を理解する意識が希薄化しているように思えます。デジタルといえど個別に最適化すればそれだけコストがかかるわけで、安易なパーソナライゼーションには持続性がありません。
逆に、UIのデジタル化により実現されるユニバーサルデザインもあります。たとえば、自動車のアクセルとブレーキの踏み間違いを、物理的に防ぐことは難しいかもしれませんが、人工知能(Artificial Intelligence:AI)により踏み間違いを検知して自動制御することは可能です。
ユニバーサルデザインの本質的な意義は、ユーザーの普遍的な課題を理解し、それをデザインで解決することにあります。自動車の例のようにUIのデジタル化によって解決される課題もありますし、UIのデジタル化によって収集される行動データが、課題の発見や解決につながることもあるでしょう。
このように、UIのデジタル化が進むこの時代においても、ユニバーサルデザインの意義は変わりませんし、その期待値はより高まるのではないでしょうか。
関連する記事
須川 敦史
UX&データスペシャリスト
クロスハック 代表 / uxmeetsdata.com 編集長
脚注
| 1. | ↑ | 再考するパーソナライゼーション |